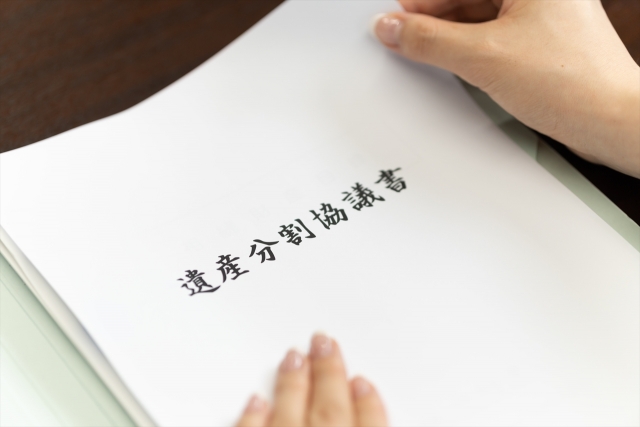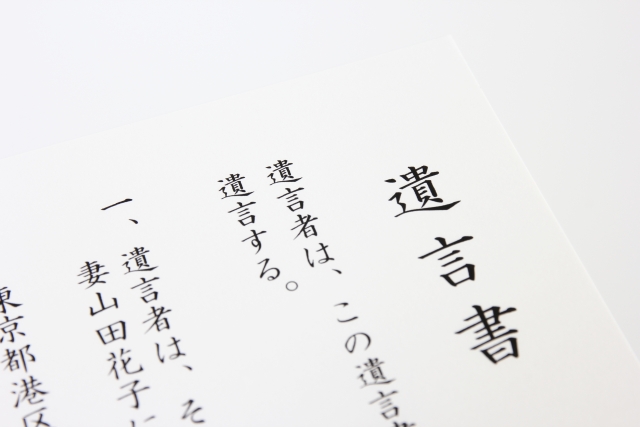相続
Information
★6/29/2024
2024年6月29日日本経済新聞の朝刊で「高齢者施設、利用料引上げ」の中でコメントが紹介されました。
★6/23/2024
2024年6月23日日経ヴェリタス第850号「介護と仕事の両立…」の中でコメントが紹介されました。
★6/22/2024
2024年6月22日介護ポストセブンで「20年ぶり新紙幣…」の記事が紹介されました。
★6/6/2024
2024年6月6日朝日新聞Reライフ.netで「65歳以上で介護保険料はどう変わる? 平均額や計算方法をわかりやすく」の記事が記載されました。
★5/28/2024
2024年5月28日介護ポストセブンで「3年ぶり介護保険法改正…」の記事が紹介されました。
★5/2/2024
2024年5月2日介護ポストセブンで「物価高騰による家計を…」の記事が紹介されました。
★5/1/2024
日本FP協会「Journal of Financial Planning 5月号」で記事が紹介されました。
★4/10/2024
2024年4月10日日本経済新聞(夕刊)の「マネーダイニング」の中でコメントが紹介されました。
★3/28/2024
2024年3月28日介護ポストセブンで「成年後見制度のデメリット…」の記事が紹介されました。
★2/23/2024
2024年2月23日介護ポストセブンで「親から子へ資産を相続したい…」の記事が紹介されました。
★1/27/2024
2024年1月27日介護ポストセブンで「高齢の親の認知症が心配。実家を売って…」の記事が紹介されました。
★1/13/2024
2024年1月13日介護ポストセブン「母親の有料老人ホーム代が毎月40万円」長引く介護の費用をどう捻出したらいい?記事が紹介されました。
★12/23/2023
介護ポストセブンで介護用のおむつ代は医療費控除の対象になるの記事が紹介されました。
★11/21/2023
介護ポストセブンで一緒に暮らしてないの母の医療費控除は受けられるの記事が紹介されました。
★10/21/2023
介護ポストセブンで差額ベット代は払わなくていいケースがある!の記事が紹介されました。
★9/26/2023
介護ポストセブンで介護帰省の交通費は工夫次第で節約できる!の記事が紹介されました。
★8/30/2023
小学館「認知症大全」の中で記事が紹介されました。
★8/28/2023
「遺言書を開封しても問題ないの?正しい対処法と注意点」の記事を監修しました。
★8/28/2023
介護ポストセブンに記事が紹介されました。
★7/27/2023
介護ポストセブンに「東京都で増加中!年金で入れる都市型軽費老人ホームとは?」の記事が紹介されました。
★7/26/2023
7月26日の読売新聞(朝刊)の「MONEY 所得に応じ税負担軽減」の中でコメントが紹介されました。
★6/9/2023
介護ポストセブンに「特別養護老人ホームは預貯金があると入所できない?」の記事が紹介されました。
★5/9/2023
介護ポストセブンに「80代の父の在宅介護にかかるお金が心配…」覚えておきたい「高額介護サービス費」の仕組みや利用方法についてが紹介されました。
★4/19/2023
介護ポストセブンに年金で入れる「ケアハウス」とは?種類や入居条件、費用、サービスを解説 入居した父親が退去を余儀なくされた実例も【FP解説】が紹介されました。
★4/16/2023
4月16日発行 日経ヴェリタス第788号「差額ベット代払わなくていい?」にコメントが紹介されました。
★3/26/2023
★3/25/2023
日本経済新聞(朝刊)の「特養の費用、減額制度で差 預貯金の変化に注意」のなかでコメントが記載されました。
★2/25/2023
介護ポストセブンに「高齢の親が入院したらいくら?」が記載されました。
★2/23/2023
東京都行政書士会の「空き家問題相談員」に認定されました。
★1/31/2023
介護ポストセブンに記事が掲載されました。
★1/12/2023
介護ポストセブンに記事が掲載されました。
★12/10/2022
介護ポストセブンに記事が掲載されました。
★11/13/2022
有料相談(タイムチャージ)をご希望の方には、無料でのお見積もりを開始いたしました。
★10/30/2022
日経ヴェリタス第764号 「介護保険知って備える」の中でコメントが紹介されました。
★9/17/2022
日本経済新聞(朝刊)で「親の介護費、資産踏まえて」のなかでコメントが紹介されました。
★9/8/2022
介護ポストセブンに記事が記載されました。
★6/25/2022
福井県のホームページに介護経験者としてのインタビューを受けました(NPO法人アラジン様主催)。
★5/15/2022
本日をもちまして、当事務所での事前復活支援金の事前確認は終了いたしました。
★5/3/2022
行政書士事務所として「事業復活支援金の事前確認は5月15日(日)を持ちまして受付終了」となります。
★3/19/2022
「日本経済新聞」(朝刊)24面、介護休業「93日」の使い方でコメントが記載されました。
★2/5/2022
カワムラ行政書士事務所で、「事業復活支援金」の事前確認を開始いたしました。詳しくはコチラ
★1/7/2022
1月15日㈯14時~16時ミニセミナーIN中野区
★9/15/2021
WEBセミナーご参加ありがとうございました(IN新宿)
「介護とお金の問題」
★9/7/2021
WEBセミナーご参加ありがとうございました(INさいたま市)
「介護とお金の問題」
★6/16/2021
行政書士事務所として「月次支援金」の登録確認機関に登録いたしました。
★5/29/2021
「日本経済新聞」(朝刊)24面にコメントが記載されました。
★3/28/2021
WEBセミナーご参加いただきありがとうございました(IN新宿)。
「人生100年時代 知らなきゃ損する!介護とお金をこう解決する」
★12/30/2020
2021年1月より「無料相談」もしくは、「有料相談」の選択制となります。
★11/11/2020
セミナーご参加いただきありがとうございました(IN名古屋)。
「人生100年時代 介護不安をどう解決するか」
★11/10/2020
セミナーご参加いただきありがとうございました(IN静岡)。
「人生100年時代 介護不安をどう解決するか」
★10/17/2020
「日本経済新聞」(朝刊)22面にコメントが記載されました。
★8/22/2020
「日本経済新聞」(朝刊)にコメントが記載されました。
★8/20/2020
「読売新聞」(朝刊)にコメントが記載されました。
★4/13/2020
マイベスト東京に記載されました。
★2/19/2020
介護ポストセブン(WEB版)にコメントが記載されました。
★7/1/2019
FPジャーナルに記事が記載されました。
★10/1/2018
★4/13/2017
週刊新潮にコメントが記載されました。
★11/25/2016
読売新聞に記事が紹介されました。
★11/4/2016
FPジャーナルに記事が紹介されました。
★8/9/2016
THE 21に記事が紹介されました。
★2/29/2016
認知症サポーターに登録
★2/18/2016
女性セブンに記事が紹介されました。
★12/21/2015
12日、21日セミナーご参加ありがとうございました。
★12/6/2015
セミナーお申し込みお早やめに。
★12/12、20日
山梨県立男女共同参画推進センターでセミナーを開催します。
★11/5/2015
女性セブンに記事が紹介されました。
★10/5/2015
提携社会保険労務士の梶原先生がテレビ朝日にマイナンバーについてのコメントが紹介されました。
★9/27/2015
大好評につき無料メール相談12月末まで延長しました。
★8/1/2015
好評につき無料メール相談9月末まで延長しました。
★7/26/2015
セミナーご参加ありがとうございました。
★7/18/2015
セミナーご参加ありがとうございました。
★7/13/2015
7月末日までメール相談無料キャンペーン実施中
★7/8/2015
suumo 介護に記事が紹介されました。
★6/5/2015
ビジネス教育出版社で7月18日(土)セミナー開催
(社会保険労務士 梶原先生とのコラボセミナーになります)
お申し込みはお早めに!
★4/22/2015
セミナーお問い合わせありがとうございます。
★3/19/2015
セミナーご参加ありがとうございました。
★2/27/2015
セミナーお問い合わせありがとうございました。
★1/19/2015
専門家紹介業をはじめました。
詳しくはお問い合わせください。
★年末年始のお知らせ
12/28/2014~1/4/2014
★12/1/2014
momに記事が紹介されました。
★11/3/2014
本日、セミナーのご参加ありがとうございました。
★10/5/2014
介護離職者5年で倍増!
当事務所では無料にて日商簿記3級、FP3級ご提供します。
★9/25/2014
介護年金エンディングプランナー
主催 NPO法人 エンディングコーディネーター協会
教育機関 メディア5
10月4日第1回受講開始
定員人数がありますので、お早めに。
★9/5/2014
介護年金エンディングプランナー認定資格開始
認定講師登録
★8/6/2014
週間新潮に記事が紹介されました。
★6/30/2014
セミナーお問い合わせありがとうございます。
★4/19/2014
セミナーIN市ヶ谷
ご参加ありがとうございました。
★3/8/2014
セミナーIN横浜
(ご参加ありがとうございました)
★2/6/2014
毎日新聞に記事紹介されました。
★12/7/2013発売
12月22日、1月7日号
婦人公論に記事が紹介されました。
★11/8/2013
セミナーIN札幌
(雨の中ありがとうございました)
★11/4/2013
セミナーINビジネス教育出版社
(雨の中ありがとうございました。)
★11/3/2013
介護離職者支援協会
賛同者等大募集
詳細はこちら
★10/30/2013
取材 中央公論新社(婦人公論)
介護とお金
(ありがとうございました)
★9/28/2013
セミナーIN株式会社マザアス、ブロードマインド少額短期保険
ありがとうございました。
★7/22/2013
セミナーINオリックス生命
(ありがとうございました)
★6/20/2013
マネーの達人 掲載
コラムの更新しました。
★6/2/2013
セミナーINビジネス教育出版社
(ありがとうございました)
★5/16/2013
毎日新聞に記事紹介されました。
★3/16/2013
セミナーIN阿佐ヶ谷
(お問合わせありがとうございました)
★3/1/2013
FINACIAL PLANNING 3月号
「介護に果たすFPの役割」
で座談会で記事紹介されました。
★2/10/2013
見つけよう新しいつながり
IN 飯田橋セントラルプラザ
★1/26/2013
セミナーIN阿佐ヶ谷
(お申し込み・お問合わせありがとうございました)
★1/7/2013
教材立ち読みコーナー開設
★1/4/2013
大声で絶対に言えない!!
介護 カネの悩み解決
10問10答
PDF版販売開始
1,050円A4版で全22頁
★11/23/2012
知らなきゃ損!!
間違いのない有料老人ホームの選び方
無料プレゼント
(お問合わせ・お申し込みありがとうございました)
★11/1/2012
介護離職者支援協会に参画
★10/21/2012
セミナーIN株式会社ニチイ学館
介護にかかるお金の話
FPによる介護費用節約術
★10/8/2012
日経ビジネス
日本を救う次世代ベンチャー100
「介護破産を防ぐベンチャー」
で紹介されました。
★10/1/2012
介護保険塾IN荻窪
(お問合わせありがとうございます)
★9/29/2012
知らなきゃ損!!
間違いのない有料老人ホームの選び方
PDF版販売開始。
1,050円 A5判で全42頁
★9/5/2012
高齢者住宅新聞
紹介記事
★8/15/2012
30分無料相談
3名様限定
(お問合わせ・お申し込みありがとうございます)
★8/1/2012
東京新聞セカンドライフ
記載記事
「遠距離介護」
★7/29/2012
介護保険塾IN阿佐ヶ谷
(お問合わせ・お申し込みありがとうございます)
★5/19/2012
無料ミニセミナー開催IN阿佐ヶ谷
(お問合わせ・お申し込みありがとうございます)
★4/28/2012
無料ミニセミナー開催IN荻窪
(お問合わせ・お申し込みありがとうございます)
★3/8/2012
サンプル版ミニセミナー
通信
(お問合わせ・お申し込みありがとうございます)
★3/3/2012
無料ミニセミナー開催IN荻窪
(お問合わせ・お申し込みありがとうございます)
★12/7/2011
本日から2012年1月31日まで
無料レター
(入院・介護に関するマメ知識・・お金編)
進呈中
メールにて送ります。
★12/3 /2011
無料相談・・12月中毎週土曜日実施中(30分)
★11/6/2011
遠距離介護セミナー参加
★10/17/2011
電話による相談実施
Copyright(C)カワムラ行政書士事務所 All rights reserved