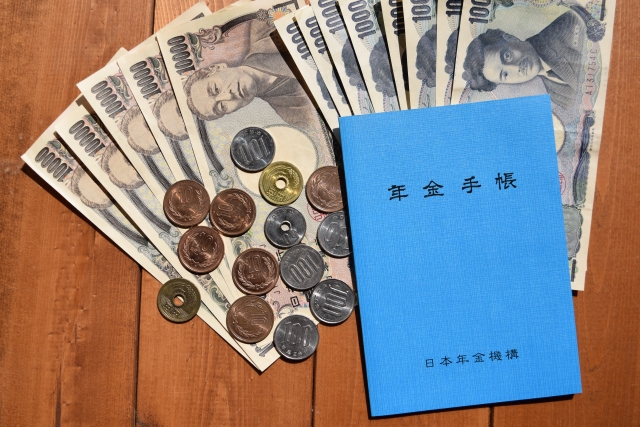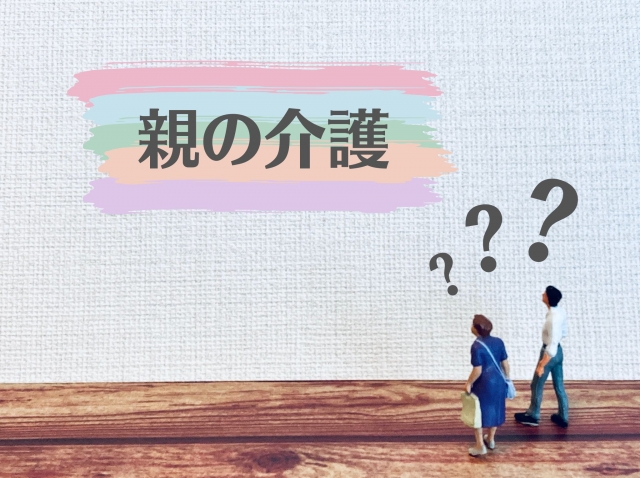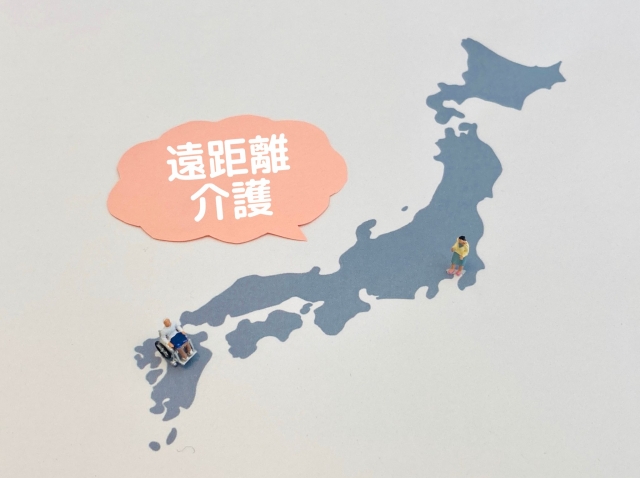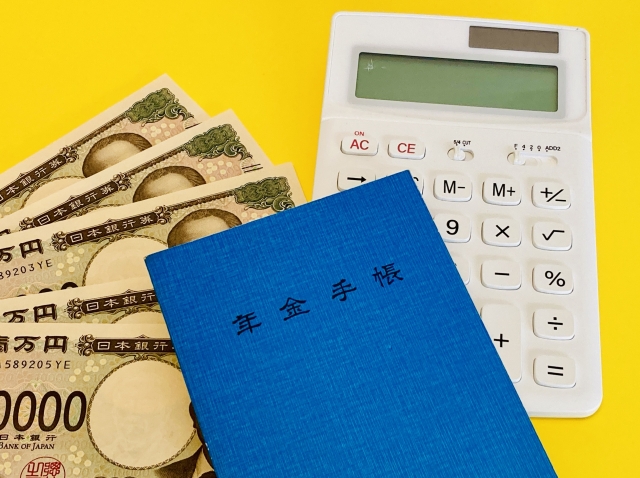介護
介護 · 2025/06/15
病院から退院を告げられてからの施設探しは、時間との戦い。焦って決めた結果、費用面や生活環境に後悔するケースもあります。たった20~30分でも、中立的な専門家に相談することで見えてくることがあります。初回20分無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください。
介護 · 2025/05/08
多くの家庭で介護に関する対策が必要となっています。特に介護費用や制度、手続きについて不安を抱える方が少なくありません。本記事では、介護費用の実態を簡潔にまとめ、どこに相談するか、どう備えるかを簡単に解説しています。初回20分無料相談受付中。お気軽にお問い合わせください。
介護 · 2025/05/06
60代から始める介護準備。将来の介護が必要になったときに困らないために、FPが介護費用や施設選び、財産管理など必要な準備について解説します。初回20分無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください。
介護 · 2025/05/02
「80代の親がリスクの高い投資を続けていて、介護費用が心配…」という方へ。投資の見直し、安全な資産管理、家族信託・後見制度に加え、家族サポート証券口座などの新制度も簡単に触れています。初回20分無料相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。
介護 · 2025/04/30
一人暮らしの親を施設に入れるかどうか、悩んだときに考えておきたいことを簡単に整理しました。気持ちを整理するヒントとしてご覧ください。
初回20分の無料相談もご利用いただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
介護 · 2025/04/28
親の介護は突然襲ってきます。費用負担に悩むことも少なくありません。40代・50代・60代それぞれの時期に合わせた備え方を知り、現実的な対策を進めることで、いざという時に慌てず安心して向き合えるようにしましょう。初回20分無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください。
介護 · 2025/04/25
将来の介護に備えたい方へ。親のこと、自分のこと、お金の不安を整理しませんか?
介護費用の見通しや財産管理、遺言作成まで、FPと行政書士の視点から一貫してサポートいたします。初回20分無料相談実施中
介護 · 2025/04/24
介護が始まると想像以上にお金がかかることも。親の介護と自分の老後資金をどう両立すればいいのか、公的制度の活用や資産管理のポイントを、今までの経験からわかりやすく解説します。初回20分無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください。
介護 · 2025/04/23
親の介護やお金のこと。
不安はあるけれど、誰に相談していいかわからない…そんな気持ち、ありませんか?
「こんなこと聞いていいのかな」と思うようなことほど、実は大事なスタートラインです。
私自身、親の介護をきっかけに「もっと早く相談すればよかった」と何度も思いました。
このブログでは、「なぜお金の相談は難しいのか」「どうやって相談を始めればいいのか」について、やさしくお話しします。
初回20分無料相談もご用意しています。話してみることで、道が見えることもあります。
どうぞお気軽にご利用くださいね。