こんにちは。ファイナンシャルプランナー(FP)・行政書士の河村修一です。
親の老老介護・遠距離介護を実際に経験した立場から、相続手続きや遺言書の作成、財産管理に加え、介護費用の見通しや保険の判断、老後資金の準備まで幅広くお手伝いしています。
「手続きとお金、両方の相談ができる窓口」として活動しています。
🟩 親の介護費用が心配な方へ
「いくらかかる?何を準備すればいい?」
✅ → 無料20分相談はこちら(初回限定)
🟦 認知症と介護にそなえる準備、進め方がわからない方へ
「何から始める?誰に相談する?」の答えがここに。
✅ → 対策サポートの詳細はこちら
🟨 相続や遺言で、親や家族のことで悩んでいませんか?
不安なまま放置せず、今から「備える」サポートを。
✅ → 遺言・相続サポートの詳細を見る
※相続手続きなどを依頼するかどうか悩んでいる人は時間に関係なく無料相談を行っています。
この記事も、そんなお悩みを持つ方のヒントになれば幸いです。
実家をどうするかは避けられないテーマ
介護や老後に備えるには「お金の準備」が欠かせません。そして、介護が長引いたときに多くのご家庭で直面するのが 「親の財産がそろそろ尽きそう」「実家をどう扱うか」 という課題です。
このような場面では、次のような疑問が出やすくなります。
-
「実家は売りたくないけれど、介護費用をどう工面するか」
-
「親が判断能力を失ったら、自宅はどうなるのか」
-
「遺言や後見制度はどこまで役立つのか」
この記事では、こうした疑問を例に挙げながら、制度の仕組みと実務上の注意点 を整理して解説していきます。
はじめに
介護が長引くと、やがて「親の資産が心もとない」「実家をどう扱うか」という現実的な課題に直面します。
ここでは、自宅活用の可否、介護ローンの契約主体の違い、後見と遺言の役割分担を、現場の視点で整理します。
自宅を売らずに活用する方法

親に判断能力があるうちであれば、自宅を「売らずに活用する」方法も検討できます。
例えば、空き家を貸し出して家賃収入を得る方法、自宅を担保にして資金を借りるリバースモーゲージ、不動産担保ローンなどです。
ただし注意したいのは、リバースモーゲージは原則として「本人が居住している住宅」が対象だという点です。
住宅金融支援機構の「リ・バース60」も同様で、契約者が実際に住んでいる自宅を担保とする仕組みになっています。
すでに施設に入っていて自宅が空き家となっている場合には、原則として利用できません。ただし例外的に、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居一時金については対象とされるケースもあります。とはいえ、介護付き有料老人ホームなどの「生活資金」には使えないため、利用できる場面は限定的です。
その場合は、不動産担保ローンや売却といった方法が現実的な選択肢になります。
判断能力を失った場合の制約

認知症などで判断能力を失ってしまうと、自宅の売却や担保設定といった契約は原則としてできません。
成年後見制度を利用すれば契約は可能ですが、家庭裁判所の許可が必要となり、売却の条件や時期も制約を受けます。
そのため、本人の意思がしっかりしているうちに備えることが重要になります。
また、任意後見契約を結んでおけば、将来判断能力を失っても財産管理を任せられるという安心感があります。
ただし、任意後見はあくまで「生前の財産管理」が対象であり、亡くなった後の相続分割には効力がありません。
相続人の中に後見人が関与している場合、その後見人は本人の利益を守る立場として法定相続分を主張せざるを得ず、柔軟な遺産分割が難しくなることがあります。
そのため「亡くなった後に誰に何を残すか」を決めておきたい場合には、やはり遺言書の準備が欠かせません。
介護ローンの「親契約」と「子契約」の違い
介護費用をまかなうために「介護ローン」を利用する方法もあります。ここで注意したいのは、誰が借りるのかによって扱いが大きく変わる点です。
-
親本人が借りる場合
借入は親の債務となり、親が亡くなれば相続財産に含まれます。結果として、実家を含む相続財産から返済に充てる必要が出てきます。実家しか大きな資産がない場合、売却して返済することになるケースが多いのです。 -
子どもが借りる場合
借入は子どもの責任となり、相続財産とは無関係です。ただし実際には返済資金をどう工面するかという課題が残ります。子どもが実家を相続した場合、売却してその資金を返済に充てる、という流れになることも少なくありません。
制度上は親本人が契約することもできますが、年齢制限や収入面の問題、また認知症による判断能力の低下から契約できないケースが多いのが現実です。そのため実務では、子どもが親の介護費用のためにローンを組むケースの方が一般的です。
相続のときに起こる問題
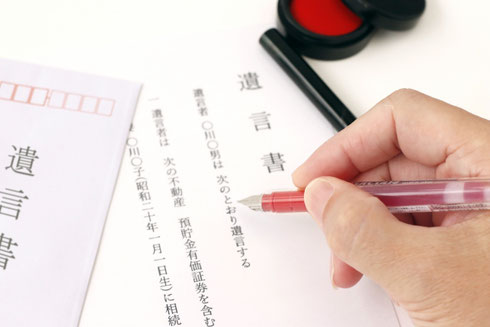
さらに、親が亡くなった後に配偶者(母親)が認知症などで判断能力を失っている場合、遺産分割協議を行うためには成年後見人を付ける必要があります。
後見制度を利用すると家庭裁判所の関与が入り、相続協議が硬直化することも少なくありません。
このような事態を防ぐには、遺言書を作成しておくことが極めて有効です。遺言があれば相続分割協議そのものを行う必要がなく、後見人が法定相続分を主張することで協議が難航するリスクを避けられます。
事前の対策が安心につながる

介護費用や実家の扱いは、相続と密接に関わるテーマです。自宅を売却したくないという気持ちは自然なことですが、リバースモーゲージは「居住していること」が条件であるため、施設に入って空き家となった自宅では原則として利用できません。結果として売却以外に選択肢がない場面も少なくありません。
そして、判断能力を失った後は後見制度の制約が大きいため、柔軟な対応は難しくなります。だからこそ、生前の財産管理には任意後見契約や家族信託を、亡くなった後の承継対策には遺言書を組み合わせて準備しておくことが、家族にとっての安心につながります。
まとめ
親の財産が尽きそうになったときに、自宅をどうするかは家族にとって非常に大きな課題です。
リ・バース60のようなリバースモーゲージは魅力的に見えますが、原則として「本人が住んでいる住宅」が条件であり、すでに施設に入っている場合には使えません。ただし例外的に、サ高住の入居一時金に限って利用できる場合があります。とはいえ、一般的な介護施設の生活費には使えないため、その場合は不動産担保ローンや売却といった現実的な方法を考える必要があります。
また、任意後見契約では相続の分割を決めることはできず、後見人は法定相続分を主張せざるを得ません。柔軟な分割を実現したいなら、遺言書を残すことが最も効果的な手段です。
介護費用や相続は一体のテーマとして考え、早めに備えておくことが家族の安心を守る第一歩となります。
当事務所では、介護費用・老後資金・相続対策をまとめて見える化するライフプラン作成 を行っています。
「初回20分の無料相談」や「キャンペーン相談」もありますので、「まずは話を聞いてみたい」という方も安心してご利用ください。ライフプラン作成はコチラ
また、介護や生活に関するさまざまなテーマについて、介護ポストセブンでも取り上げています。こちらの記事もぜひご覧ください。
メディア掲載実績
私のコメントや情報提供を行った記事が、以下のメディアに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。
【過去の一部の相談事例】
・介護費用がどれくらいかかるのか不安(50代女性)
・老後を見据えたライフプラン作成(50代)
・親の遺言書・生前贈与について(40代男性)
・資産運用について基本を整理したい(60代女性)
・介護費用に関連する補足給付について(50代女性)
・医療費控除の概要について(50代女性)
・親の有料老人ホームの費用に関するキャッシュフロー表作成(50代夫婦)
・親の収入や資産から子どもへの援助に関するキャッシュフロー表作成(50代女性)
・親の保険と介護費用に関するご相談(50代女性)
・自宅の民事信託の活用と概要について(50代男性)
・所得控除と介護費用の関連について(60代女性)
・金融機関の解約手続きについてのご相談(60代女性)
・遺産分割協議書の作成に関するご相談(60代女性)
・親の介護費用と一時払終身保険の活用について(50代女性)
・老後資金のキャッシュフロー表作成(60代男性)
・年金受給に関するご相談(60代男性)など
