こんにちは。ファイナンシャルプランナー(FP)・行政書士の河村修一です。
親の老老介護・遠距離介護を実際に経験した立場から、相続手続きや遺言書の作成、財産管理に加え、介護費用の見通しや保険の判断、老後資金の準備まで幅広くお手伝いしています。
「手続きとお金、両方の相談ができる窓口」として活動しています。
🟩 親の介護費用・自分の老後が心配な方へ
「いくらかかる?何を準備すればいい?」
→ ライフプラン作成サービスへ
(親の年金・資産・施設費用を見える化して不安を安心に)
🟦 認知症になる前の財産対策を考えたい方へ
「家のこと、お金の管理、きょうだいとの話し合い…どう進める?」
→ 親の認知症と介護費用に備えるサポートプラン
🟨 相続や遺言について準備したい方へ
「遺言の準備も、相続手続きも一人で悩まない」
→ 遺言書の作成支援・相続手続きサポートへ
この記事も、そんなお悩みを持つ方のヒントになれば幸いです。

親の介護が現実味を帯びてくる50代・60代。
そんな中で「自分はいつ退職するか?」という選択が、実は親の介護資金や自分の老後設計に大きな影響を与えることをご存じですか?
介護費用が必要になるかもしれない時期にこそ、雇用保険や年金制度の使い方で、将来使えるお金が数十万円単位で変わってくることもあります。
つい先日、このような質問をいただきました。
「64歳11カ月で退職するのと、65歳ちょうどで退職するのでは、雇用保険の扱いが違うと聞きました。本当ですか?」
これは、50代・60代の相談現場で必ずといっていいほど聞かれるテーマです。
この問いに答えるには、雇用保険(失業給付)の仕組みを理解しておくことが大切です。
特に65歳を境に、受け取れる給付の内容と金額が大きく異なります。
今回は「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違いを中心に、制度のポイントと損得をわかりやすく解説します。
65歳未満で退職した場合|基本手当(失業手当)が受け取れる
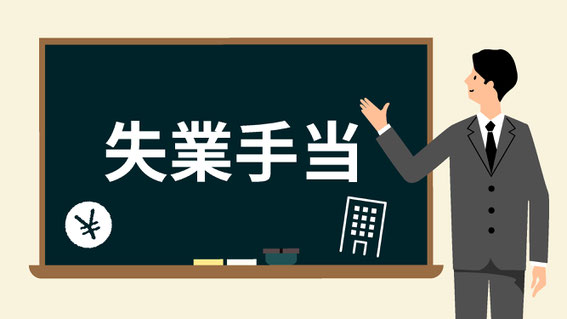
65歳未満で退職した人は、「雇用保険の被保険者」であれば、一般の失業給付である「基本手当」が支給されます。
支給要件は、原則として過去2年間に12か月以上の被保険者期間があること(自己都合退職の場合)。
受給日数は年齢や勤続年数などで異なり、下記のようになります。
| 勤続年数 | 受給日数(例:自己都合) |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
※特定理由離職者や会社都合退職の場合、日数はさらに手厚くなります。
※自己都合退職の場合、被保険者期間が1年以上3年未満であれば90日、10年以上で120日、20年以上で150日が目安となります。
基本手当の金額は、退職前6か月の賃金日額の45~80%が目安。
年齢や給与によって上限がありますが、日額で約6,000円~8,500円程度の支給を受けられることもあります。
なお、日額は年齢によって上限があり、例えば「60歳以上」の場合の上限は2024年度で7,186円/日です。
65歳以上で退職した場合/一時金の「高年齢求職者給付金」に
65歳以降に退職した場合、受け取れるのは「高年齢求職者給付金」です。
これは「一時金」であり、支給額や制度の柔軟性において、基本手当と大きな差があります。
一時金支給額は、退職時の賃金日額をもとに「30日分〜50日分」として計算されます。たとえば、賃金日額が6,000円の場合は18万円〜30万円前後になります。
つまり、65歳を超えると雇用保険の「保障力」が弱まるということです。
どちらが得なのか?比較のポイント
| 比較項目 | 65歳未満 | 65歳以上 |
| 支給種別 | 基本手当(分割支給) | 高年齢求職者給付金(一時金) |
| 支給金額 | 数十万円~100万円超も | 約10万円~30万円程度 |
| 再就職手当 | あり | なし(給付金自体が一時金) |
| 併給制限 | 年金等との併給調整あり | なし(一時金のため) |
雇用保険の「基本手当(いわゆる失業手当)」は、65歳未満で退職した方が対象です。
しかも、再就職が早ければ「再就職手当」という一時金がもらえることもあるんです。
この再就職手当は、基本手当の残り日数に応じて金額が決まり、早く再就職するほど多く受け取れます。そのため、65歳になる前に退職して基本手当+再就職手当を活用した方が、トータルでは有利になるケースが多いのです。
※Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~厚生労働省
ただし、ここで気をつけたいのが「退職理由」や「退職金の取り扱い」です。
たとえば、会社の規定で「自己都合退職だと退職金が減額される」ケースや、「早期退職は対象外」などの条件がある場合も。
制度だけを見て退職を急ぐと、逆に損をしてしまうこともあるため注意が必要です。
実際に退職を検討する際は、
-
会社の退職金規程や就業規則の確認
-
ハローワークでの受給資格の確認
-
ご自身の年金受給状況や再就職の見込み
などを踏まえて、総合的に判断するのが安心です。
※再就職手当は、65歳未満で基本手当を受給している方が、早期に再就職した場合に支給されます。ただし、再就職先でも65歳未満であることが条件です。
年齢のカウントに注意/法律上は「誕生日の前日」に年齢加算
「64歳11ヶ月で退職したつもりが、制度上は65歳扱いだった!」というケースも。
年齢計算に関する法律では、「誕生日の前日」に65歳に達するとされます。
したがって、65歳に達する「前」=誕生日前々日までに退職しなければ、雇用保険の基本手当(失業給付)の対象にはなりません。
退職日が誕生日前日や当日ではすでに65歳到達後とみなされ、基本手当の支給対象外となる点に注意が必要です。
つまり、65歳の誕生日当日はすでに65歳ですので、退職日は「誕生日の前々日」までに設定しておく必要があります。
まとめ

年金についても、退職後の生活費や介護支出をどう捻出するかを考えるうえで重要です。
たとえば、年金の繰下げ受給を選ぶと毎月の年金額は増えますが、それまでの生活費や介護費用をどこから捻出するかが課題になります。
一方、繰上げ受給をすると金額は減るものの、早期に現金収入を確保できます。
「いつ受給するか」は、「何にお金がかかるか(例:親の介護、住まいの支援)」とセットで考える必要があります。
65歳という節目をどう迎えるかによって、雇用保険の給付額や年金受給のタイミングが変わり、将来使えるお金に大きな差が生まれます。
とくに親の介護が視野に入ってきた方にとっては、「いつ退職するか」「いつ年金をもらい始めるか」が、介護支援の選択肢や家計の安定に直結します。
退職時期をただ年齢で決めるのではなく、
✔ 雇用保険(基本手当)
✔ 年金の繰上げ・繰下げ
✔ 親の介護や支援に必要な費用
などをふまえて、総合的に判断することが大切です。
不安がある方は、介護費用と老後資金の両面からアドバイスできるファイナンシャルプランナーに相談してみてください。
制度を正しく知り、今できる準備をしておくことで、家族と自分の将来に安心が生まれます。
※制度の改正が行われることもあるため、実際の受給要件や金額については、退職前に必ずハローワーク等で確認しましょう。
また、介護や生活に関するさまざまなテーマについて、介護ポストセブンでも取り上げています。こちらの記事もぜひご覧ください。
メディア掲載実績
私のコメントや情報提供を行った記事が、以下のメディアに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。
【過去の一部の相談事例】
・介護費用がどれくらいかかるのか不安(50代女性)
・老後を見据えたライフプラン作成(50代)
・親の遺言書・生前贈与について(40代男性)
・資産運用について基本を整理したい(60代女性)
・介護費用に関連する補足給付について(50代女性)
・医療費控除の概要について(50代女性)
・親の有料老人ホームの費用に関するキャッシュフロー表作成(50代夫婦)
・親の収入や資産から子どもへの援助に関するキャッシュフロー表作成(50代女性)
・親の保険と介護費用に関するご相談(50代女性)
・自宅の民事信託の活用と概要について(50代男性)
・所得控除と介護費用の関連について(60代女性)
・金融機関の解約手続きについてのご相談(60代女性)
・遺産分割協議書の作成に関するご相談(60代女性)
・親の介護費用と一時払終身保険の活用について(50代女性)
・老後資金のキャッシュフロー表作成(60代男性)
・年金受給に関するご相談(60代男性)など