将来への不安が高まる中、現在は年2~3%のペースで物価が上昇しています。
一方、銀行の1年もの定期預金の金利はおよそ1%程度。
つまり、預けていてもお金の実質的な価値は目減りしてしまうことになります。
このように、現金や預金はインフレに弱いという特性があります。
とはいえ、株式や投資信託は値動きが大きく、元本割れのリスクがあるため、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
たとえば、「将来の親の介護費用」など、1~2年後に必要になるかもしれないし、いつ使うことになるか分からないお金を安全に運用しておきたい場合には、個人向け国債のように元本保証のある金融商品を選ぶことで、安心して備えることができます。
このように元本の減らない商品に興味を持つ方から、以前こんなご質問をいただきました。
「個人向け国債って安全なんですか? どこで買えるんですか?」
このブログでは、こうした疑問にお答えしながら、個人向け国債がどんな仕組みで、どんな人に向いているのかをわかりやすくご説明します。
なお、介護費用は一例であり、他にも「子どもの教育資金」や「老後の生活費」など、目的に応じて検討する手段の一つになります。
国が発行する、安全性の高い商品
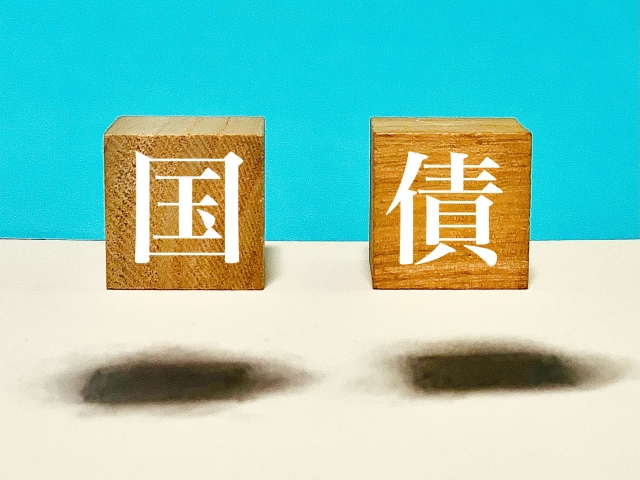
個人向け国債は、その名のとおり「国」が発行する債券です。
初めて発行されたのは2003年3月で、最初の債券は10年満期の変動金利型でした。
現在では、この「変動10年」に加えて、固定金利型の「固定3年」「固定5年」があり、合計3種類が用意されています。
発行頻度は、当初は3カ月に1度でしたが、現在では毎月発行されています。
仕組みとしては、私たちが国債を購入することで、国にお金を貸し、一定期間後に国が元本と利子を返してくれるというものです。
利子は半年ごとに支払われ、満期を迎えると、最初に投資した金額(元本)がそのまま戻ってくるため、安心感があります。
企業が発行する社債と異なり、国が破綻する可能性は極めて低く、個人向け国債は安全性の高い金融商品とされています。
「変動10年」の最大のポイントは、市場金利に連動して半年ごとに利率が見直されることです。
半年ごとに支払われる利子は、10年長期国債発行の利回りを基準利率と定め、これに0.66%をかけた水準で決定されます。
つまり、将来的に金利が上昇しても、低金利に縛られることなく利率が見直される点が魅力です。
一方、「固定3年」や「固定5年」の利率は、募集が始まる直前における期間3年ないし5年物固定利付国債の金利を基準金利として定められますが、それぞれ3年物は0.03%、5年物は0.05%を控除した水準として定められています。
固定金利型は金利が上がった場合に不利となり、またインフレにも弱いという特性があります。
なお、「変動10年」「固定5年」「固定3年」のいずれも、計算された利回りが0.05%を下回る場合でも、「最低金利0.05%」が保証されています。
中途換金できる安心感
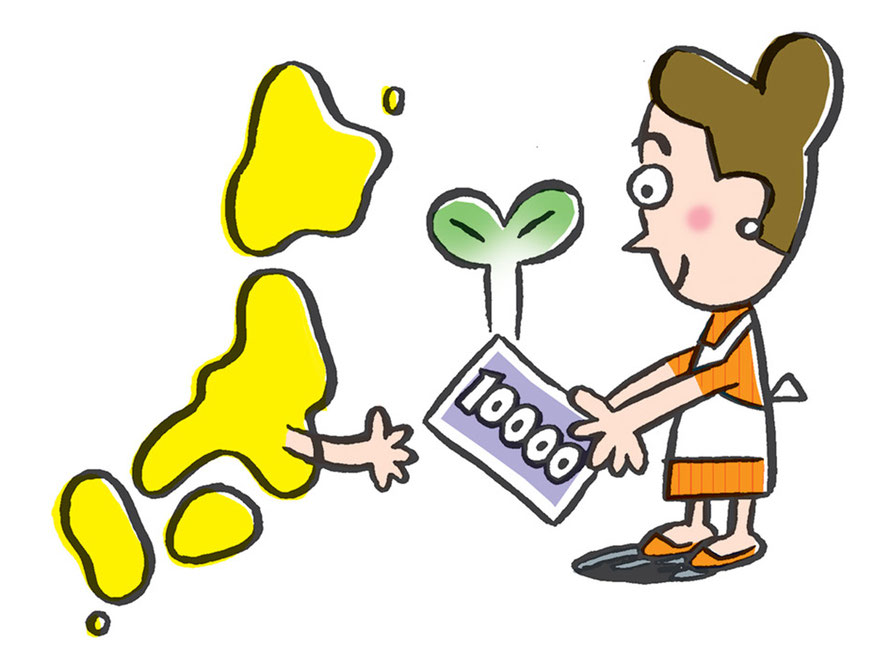
「でも、10年も待てない」「急にお金が必要になったらどうしよう」と不安に思う方もいるかもしれません。
個人向け国債は、発行から1年が経過すれば中途換金が可能です。
しかも、換金しても元本割れのリスクはありません。
直近2回分の利子を差し引く形で、国が額面で買い取ってくれます。
具体的には、1年を過ぎた後であれば、直前2回(1年)分の利子相当額(税引前)に0.79685をかけた金額を手数料として支払えば、いつでも換金できます。
つまり、急にお金が必要になったときにも、安心して現金化できる仕組みです。
金融商品によっては、「途中で売ろうとしたら価格が下がっていて損をした」というケースも珍しくありませんが、個人向け国債にはそのような心配がありません。
「すぐ使う予定はないけれど、普通預金に置いたままのお金がある」という方にとっては、安心感と利回りを兼ね備えた、検討に値する商品といえるでしょう。
個人向け国債の購入方法

個人向け国債は、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、ゆうちょ銀行、証券会社、農業協同組合など、さまざまな金融機関で購入できます。
都市銀行や地方銀行、信用金庫などの店頭では、担当者と相談しながら購入することができます。
一方で、楽天証券やSBI証券などのネット証券、あるいはオンライン申し込みに対応している銀行などを利用すれば、自宅にいながら手続きができるため、手軽さや利便性を重視する方に適しています。
また、証券会社の中には、期間限定で購入者に現金をプレゼントするキャンペーンを実施しているところもありますので、購入するときには念のため調べてみてはどうでしょうか。
① 購入に必要な手続き
初めて個人向け国債を購入する場合、購入を希望する証券会社や銀行、郵便局で「国債専用口座」を開設する必要があります。
口座開設時には、本人確認書類(運転免許証や健康保険証)、マイナンバー(個人番号)、印鑑などが必要です。
また、国債を購入する際には、購入代金、預金通帳、印鑑も必要になります。
詳しい手続きについては、口座を開設する金融機関に直接お問い合わせください。
② 口座開設と手数料
個人向け国債を含む振替国債は、証券会社、銀行、郵便局などで開設された専用口座で管理されます。
ただし、金融機関によっては、口座開設や維持等に際して手数料がかかる場合があります。
口座開設には数日かかることもあるため、余裕を持って手続きを行うことをお勧めします。
詳細については、各金融機関にお問い合わせください。
③ 購入購入申し込みについて
国債は発行日の前に設けられた募集期間中に購入申し込みができます。
ただし、取り扱う国債の種類や募集期間は金融機関によって異なりますので、具体的な情報については事前に各金融機関に確認してください。
※ 参考 個人向け国債 財務省
資産運用の入り口としても活用できる
「個人向け国債、どうも踏ん切りがつかない」という方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、大きな利回りを期待する商品ではありませんが、重要なのは「リスクを取らずに、確実にお金を守りたい」という目的に合っているかどうかです。
投資初心者の方が、いきなり株式や外貨建て保険などに手を出すよりも、投資の入り口として個人向け国債を選ぶのは、堅実な選択と言えるのではないでしょうか。
なお、個人向け国債は、最低1万円から、1万円単位で購入できます。
まとまった資金がなくても始めやすいため、「少額で試してみたい」「老後資金の一部だけ運用してみたい」と考える方にも適しています。
金利は低めですが、何もしないで普通預金に置いておくより有利な場合もありますし、「安全に資産を持ち続けられる」という心理的な安心感も、大きなメリットのひとつです。
| 商品名 | 変動10 | 固定5 | 固定3 |
| 満期 | 10年 | 5年 | 3年 |
| 金利タイプ | 変動金利 | 固定金利 | 固定金利 |
| 金利設定方法 | 基準金利×0.66 | 基準金利-0.05% | 基準金利-0.03% |
| 金利の下限 | 0.05% | ||
| 利子の受け取り | 半年ごとに年2回 | ||
| 購入単価(販売価格) | 最低1万円から1万円単位(額面100円につき100円) | ||
| 償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ) | ||
| 中途換金 | 発行後1年経過すれば、いつでも中途換金可能。直近2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。 | ||
| 発行月(発行頻度) | 毎月(年12回) | ||
介護に向けた資金準備をどうするか?

個人向け国債のように元本保証があり、安全性の高い商品は、「今すぐ使う予定はないけれど、将来確実に必要になるお金」の準備に適しています。
特に、高齢の親の介護費用に備える場合には、ある程度まとまった資金があるほど、こうした安定した商品を活用するメリットは大きいのではないでしょうか。
高齢の親を想定した場合、まとまったお金を株式などのリスク資産で運用すると、いざ介護が必要になったタイミングで元本割れしている可能性もあります。
つまり、資産運用に必要な「たとえば、10年以上の長期運用期間」を確保するのが難しいケースも少なくありません。
そうした状況では、値動きのある商品よりも、価格変動リスクの小さい安定性の高い商品で備えておく方が現実的です。
介護は突然始まることが多く、いざお金が必要になったときに資産が目減りしていたら、大きな支障をきたします。
だからこそ、「元本割れのリスクを避ける」視点を持ち、安全性の高い商品を選ぶことが重要です。
個人向け国債は、その選択肢の一つとして十分に活用できます。
私のもとにも、「介護費用が心配」「親のお金をどう守ればいいかわからない」といったご相談も寄せられます。
お金の使い方や準備の方法に迷ったときは、一人で悩まず、専門家に相談してみることをおすすめします。
どんな資産を、どのくらいの期間、どのような形で備えるのか。
今できることから、一歩ずつ考えていきましょう。
また、もし今、親の介護が心配なら、ぜひ一度、「介護とお金そなえプラン」を検討してみてください。
あなたとご家族の未来の安心をサポートします。
介護や生活に関するさまざまなテーマについて、介護ポストセブンでも取り上げています。こちらの記事もぜひご覧ください。
メディア掲載実績
私のコメントや情報提供を行った記事が、以下のメディアに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。
【過去の一部の相談事例】
・介護費用がどれくらいかかるのか不安(50代女性)
・親の遺言書・生前贈与について(40代男性)
・資産運用について基本を整理したい(60代女性)など
・介護費用に関連する補足給付について(50代女性)
・医療費控除の概要について(50代女性)
・親の有料老人ホームの費用に関するキャッシュフロー表作成(50代夫婦)
・親の収入や資産から子どもへの援助に関するキャッシュフロー表作成(50代女性)
・親の保険と介護費用に関するご相談(50代女性)
・自宅の民事信託の活用と概要について(50代男性)
・所得控除と介護費用の関連について(60代女性)
・金融機関の解約手続きについてのご相談(60代女性)
・遺産分割協議書の作成に関するご相談(60代女性)
・親の介護費用と一時払終身保険の活用について(50代女性)
・老後資金のキャッシュフロー表作成(60代男性)
・年金受給に関するご相談(60代男性)など
